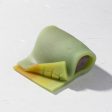今年の夏至は6月21日でした。
夏至といえば、日本では節季という括りでなくとも冬至や秋分、春分の日などとともに年中の季節の言葉として、知らない人はない時期ではないでしょうか。
この一年で最も日が長く、夜が短い1日を皆さまはどのように過ごされましたか。
今年の6月21日は午前中曇り空で、午後から日の差す貴重な梅雨の晴れ間でした。有斐斎弘道館ではこの時期は、毎年生い茂る木々とともに伸び盛りの雑草と格闘する日々です。21日だけでなく昨日もこうしてピンセットを持ちながらの細かい草引きをしていました。

草引き自体もなかなか作業としては大変ながら楽しいのですが、この時期に咲く花々も心和ませてくれます。
柘榴、トウギボウシ、クチナシ、紫陽花など。柘榴の盛りは終わってしまいましたが、露地庭の中程壁側にあるクチナシは、ちょうどたくさんの花をつけていました。恥ずかしながら草花に不案内なのですが、当館のクチナシの花が同じ木に白いものに混じって薄黄色のものもあり不思議に思っていましたら、クチナシの花というのは最初は純白から始まり、徐々に黄色に色をつけて最後に茶色くなり散っていくのだそうです。確かによく見ると黄色の方が少し日が立っているようで、足元には完全に茶色くなって落ちた花が落ちていました。拾い上げて見ると、香りはまだ濃厚に立ち上がり、花は朽ちてもまだ生命が残っているようです。紫陽花もそうして考えると咲き始めから満開までゆっくりと日をかけ、さらに時期によって色を変えていくので、この時期に咲く花は日の長さとともにそれぞれの盛りや命も生きながらえるものが多いのかもしれませんね。





夏至の候は
初侯 乃東枯る(なつかれくさかれる)
次候 菖蒲華さく(あやめはなさく)
末候 半夏生ず(はんげしょうず)
どの候も植物について語っています。
やはりこの時期は梅雨の到来とともに草花の盛衰が目立つ時期、ということでしょうか。
これからの有斐斎弘道館では、毎年恒例となっている京菓子展の公募が7月1日より始まります。今年は「手のひらの自然–源氏物語」です。これから京菓子展のFacebookでも源氏物語や京菓子展に関するさまざまな情報をお伝えしていく予定ですので、当館の他にもぜひ京菓子展のFacebookにもご注目ください。