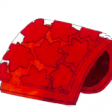夕顔の花を介して、歌のやりとりをした源氏でしたが、その女主人の身元が分かりません。大弐の乳母の子である乳母子(側近の家臣としておきます)惟光に探らせます。
女の身元が分かる間、「夕顔」巻ではさまざまな女とのやりとりが語られます。
空蝉は出自と紀伊の守の妻という運命によってこころから源氏を愛せない懊悩が語られ、また、六条にいる高貴な女との逢瀬も語られます。(そう六条御息所とよばれる方です。)
さて、その惟光の手引きで夕顔の女の家にお泊まりと言うことになりました。言葉をかわすほどに、源氏は夕顔の女がいとおしくなります。一方で、五条の下町はなんともやかましい夜でした・・・。
八月十五夜、隈なき月影、ひま多かる板屋残りなく漏り来て、見ならひたまはぬ住まひのさまもめづらしきに、暁近くなりにけるなるべし、隣の家々、あやしき賤(しづ)の男の声々、目さまして、「あはれ、いと寒しや」「今年こそなりはひにも頼むところ少なく、田舎の通ひも思ひかけねば、いと心細けれ、北殿こそ、聞きたまふや」など、言ひかはすも聞こゆ。いとあはれなるおのがじしのいとなみに、起きいでてそそめき騒ぐもほどなきを、女いと恥づかしく思ひたり。艶だちけしきばまむ人は、消えも入りぬべき住まひのさまなめりかし。されど、のどかに、つらきも、憂きも、かたはらいたきことも、思ひいれたるさまならで、わがもてなしありさまは、いとあてはかにこめかしくて、またなくらうがはしき隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、なかなか恥ぢかかやかむよりは、罪許されてぞ見えける。こほこほと鳴(な)る神(かみ)よりもおどろおどろしく、踏みとどろかすから臼(うす)の音も、枕上(まくらがみ)とおぼゆる、あな耳かしがまし、とこれにぞおぼさるる。何の響きとも聞き入れたまはず、いとあやしうめざましきおとなひとのみ聞きたまふ。くだくだしきことのみ多かり。
近所のおっさんの、「なあ!寒いなあ!」とか言う声が丸聞こえだったり、生活音がすごく聞こえます。はじめはめずらしがっていた源氏も我慢がならなくなり、別の所へ行こう!と夕顔を連れ出してしまいます。
若い男女が、屋敷をぬけて人目のつかないところへランデヴーです。どこに行くのかと思ったら、なんと廃墟に連れ出してしまいます。このあいだ、すこし不吉な空気が物語全体を包み込むようになります。夕顔はそれを察知したのか少しおびえるようになります。源氏は彼女の様子にも、なんとなく薄気味悪い情景にも深く思い至りません。源氏の目には夕顔の女との密会しかみえていませんでした。
廃墟といえど、管理者はいましたから、そのものに中をととのえさせます。
夕顔は空恐ろしさが抜けないながらも、源氏の愛を受け止めます。
たとしへなく静かなるゆふべの空をながめたまひて、奥のかたは暗うものむつかし、と女は思ひたれば、端の簾をあげて添ひ臥したまへり。夕ばえを見かはして、女もかかるありさまを、思ひのほかにあやしきここちはしながら、よろづの嘆き忘れて少しうちとけゆくけしき、いとらうたし。
そこで、源氏達はそのまま一夜をすごしました。
ところが、です。源氏の夢枕に美しい女が座っていました。こんなことを言います。
「おのが、いとめでたしと見たてまつるをば、尋ねおもほさで、かくことなることなき人を率ておはして、時めかしたまふこそ、いとめざましくつらけれ」とて、この御かたはらの人をかき起こさむとすと見たまふ。ものに襲(おそ)はるるここちして、驚きたまへれば、火も消えにけり。
「貴方ヲステキナ方トオモッテイル人ニ、アイニコナイデ、コンナトコロデコンナ女ヲカワイガッテイラッシャルナンテ、ナントネタマシク恨メシイコトデショウ」と、隣に寝ている女を襲おうとしていたのではっと目覚めると、明かりもフッときえてあたりは真っ暗です。
これは魔の仕業。察した源氏は、様々に魔除けの行いをしますが、夕顔の女を置いていってしまいました・・・。
かい探りたまふに、息もせず。ひき動かしたまへど、なよなよとして、われにもあらぬさまなれば、いといたく若びたる人にて、ものにけどられぬるなめり、とせむかたなきここちしたまふ。
夕顔の女は反応がありません。怖がれば怖がるほど心霊現象は起こるとはいいますが、夕顔も幼げで、怖がりであったために、もののけに魅入られたのではないかと源氏はかんがえてしまいます。取り返しのつかないことになったのではないか。
召し寄せて見たまへば、ただこの枕上(まくらがみ)に夢に見えつる容貌(かたち)したる女、面影に見えて、ふと消え失せぬ。(略)まづこの人いかになりぬるぞとおもほす心騒ぎに、身の上も知られたまはず、添ひ臥して、「やや」と驚かしたまへど、ただ冷えに冷え入りて、息はとく絶えはてにけり。言はむかたなし。たのもしく、いかにと言ひふれたまふべき人もなし。
なんとか紙燭の火をもってこさせてまわりの様子をみます。すると、さきほど夢に出て来た女がフッと消えました。ずっと様子を見ていたのでしょう。怖いですね・・・。一方、夕顔の女は動かせど、身体は冷え行くばかり。夕顔の死。取り返しのつかないことにいよいよなりました。しかし、頼れるものはここにはいません。源氏は取り乱します。
さこそ強がりたまへど、若き御心にて、言ふかひなくなりぬるを見たまふに、やるかたなくて、つと抱きて、「あが君、生きいでたまへ、いといみじき目な見せたまひそ」とのたまへど、冷え入りにたれば、けはひものうとくなりゆく。
「貴女よ!生き返りたまへよ!そんなひどいことなさらないで!」と叫んでも状況は変化しません。
二人を邪魔してはと、下がっていた惟光がやっと戻ってきました。源氏は今まで張っていた気が緩んで大泣きしてしまいます。17歳の青年です。目の前で愛する女が死んだというのは余りに酷な状況でしょう。
その後、惟光によって様々な処理がなされますが、源氏は文字通り生きる気力を無くして寝込んでしまいまうのでした・・・。
「夕顔」の巻において、「帚木」、「空蝉」と続いてきた物語は、一応キリがよく幕を閉じます。
それは物語のはじめにかたられた、空蝉の下向(地方長官である夫について、都をさるのでした)によってケリが付けられます。帚木三帖において、空蝉と夕顔が交錯し、双方が物語から退場していくのです。
さて、こうして、幕が閉じたわけですが、これは若かりし光源氏の、若気の至りのようなエピソードです(人が死んでいますが・・・。)。少しでてきた六条御息所や、葵の上など、まだまだ伏線は回収されていません。
物語は源氏の人生に関わる恋へと変容していきます。
※源氏物語本文は日本文学web図書館 平安文学ライブラリーの本文を用いました。
御手洗靖大(早稲田大学大学院文学研究科 M1)