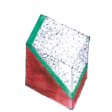空蝉との一件はとりあえず終わって(その後も手紙のやりとりなどでちょくちょく出て来ます)もう一人の女の話へと物語は展開していきます。
六条わたりの御忍びありきのころ、内裏(うち)よりまかでたまふ中宿りに、大弐の乳母のいたくわづらひて、尼になりにける、とぶらはむとて、五条なる家尋ねておはしたり。
内裏から六条のあたりにいる女のところへ行く途中、光源氏の育ての親である乳母が病気となったので、お見舞いに五条へ寄ることになりました。
五条のあたりは、当時、庶民的な下町だったようです。家についても鍵が閉まっているので、牛車で待っていると、隣の質素な家に、美しい花をみつけました。
少しさしのぞきたまへれば、門は蔀(しとみ)のやうなるおしあげたる、見入れのほどなくものはかなき住まひを、あはれに、いづこかさしてと思ほしなせば、玉の台も同じことなり。
切り掛けだつものに、いと青やかなる葛(かづら)のここちよげにはひかかれるに、白き花ぞ、おのれひとり笑みの眉ひらけたる。「遠方人(をちかたびと)にもの申す」と、ひとりごちたまふを
「白き花ぞ、おのれひとり笑みの眉ひらけたる」という表現がかわいいですね。「遠方人(をちかたびと)にもの申す」とは、「うちわたす遠方人にもの申すわれ そのそこに白く咲けるは何の花ぞも」という歌謡の一節です。「そこに咲く白い花はなんですか~」と言う意味で歌っているのですね。
源氏は記念に花をもらってきなさいとおつきの者に言います。すると、その家からかわいらしい少女が出て来ました。この場面はよく絵画化される場面です。
黄なる生絹(すずし)の単袴(ひとへばかま)長く着なしたる童の、をかしげなるいで来て、うち招く。白き扇のいたうこがしたるを、「これに置きてまゐらせよ、枝もなさけなげなめる花を」とて取らせたれば、
高貴なお方に、この扇にのせて我が家の夕顔を差し上げてくださいまし。枝もありませんので。といいます。源氏は高貴なお方ですから、手渡しはできません。草花の多くは枝につけてさしあげるものですが、それが無いので扇でどうぞ、というのでしょう。なんとも心の行き届いた風流な計らいです。
さて、やはり、その扇には歌が書かれていました。源氏はお見舞いを終えて、歌を読み、普通の女ではないことを思います。
心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花
心当てにそれかとぞ見るとは、これかなあ・・・とおもってこれと見ると言うことです。「ぞ」という係り結びの言葉があり、見るにかかります。ここで文が切れるのですね。そうして、「白露の光がついた夕顔の花を」と倒置法になっています。訳としては「貴方がご覧になったのはこれかなあとおもって見ています。いま差し上げた白露の光のついた夕顔の花を」というふうになるでしょうか。
相手方は女主人の家で、家の前にとまっているのが源氏だと知らないのでしょう。とりあえず高貴な公達が来たと思っています。なので、まあ逆ナンの歌でしょう。下町になんだか公達が来たみたい。しかも家の夕顔がほしいといっておられる。挨拶の歌でもおくっておかねば!と考えたのでしょうね。これは、源氏が「遠方人(をちかたびと)にもの申す」、つまり、むこうのあなたにお尋ねします、この花はなんですか?といったのにこたえた歌とみるべきでしょう。(この歌については古来、諸説ありますが、和歌として読むと、この解釈でいいのではないかと思っています。)
そこで源氏は返歌をします。
寄りてこそそれかとも見めたそかれにほのぼの見つる花の夕顔
いやあ、そんなこと言われてもわからないなあ、家によっていってこそ私の見ていた夕顔と分かるでしょうね。黄昏にほのぼの見えている夕顔よ、と訳しました。たそかれにほのぼの見つる花の夕顔は、源氏の記憶の中にある、女の家の夕顔の花でしょう。
私は和歌の人間なので、ここら辺はいろいろと思うところがあるのですが、歌のやりとり(贈答といいます)というのは、返歌によって完成します。贈歌はさまざまな文脈を持つのですが、それが返歌する人によって解釈され、意味が決まるのですね。
贈歌は、結句(歌の末尾)が夕顔の花となっており、どうしてもそちらに目が行って、歌の本質も「光そへたる夕顔の花」であると思われがちです。そうして夕顔の花が何か意味深なものとなっているという読みをさそいます。(これまでの研究も、夕顔の花は誰のことかというものが多くあり、いろいろ提示されました。)
けれども、返歌によって、やりとりは夕顔という花を媒介とした男女の駆け引きであることがわかってきます。つまり見るべき所は「心当てにそれかとぞ見る」。あなたが見てたのはこれですかね?というところです。それに対する「寄りてこそそれかとも見め」とは、あなたの家に行ってみないと分からない、と言っています。通う口実ですよね。このような和歌によるコミュニケーションを読み取りたく思います。
※源氏物語本文は日本文学web図書館 平安文学ライブラリーの本文を用いました。
御手洗靖大(早稲田大学大学院文学研究科 M1)